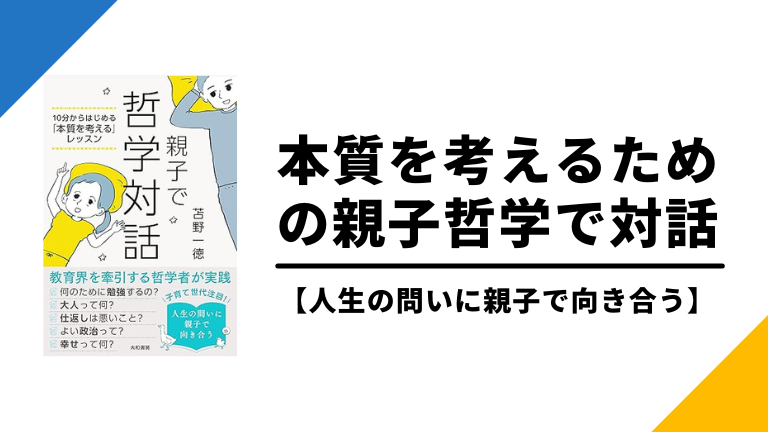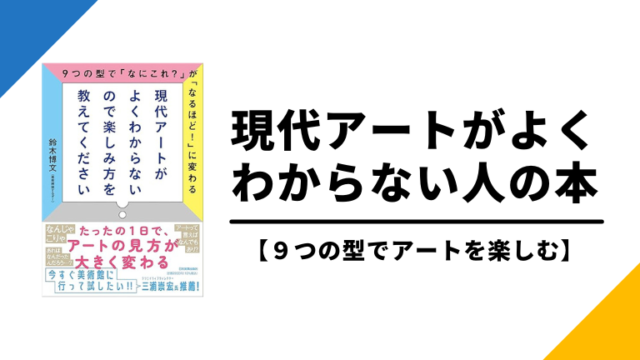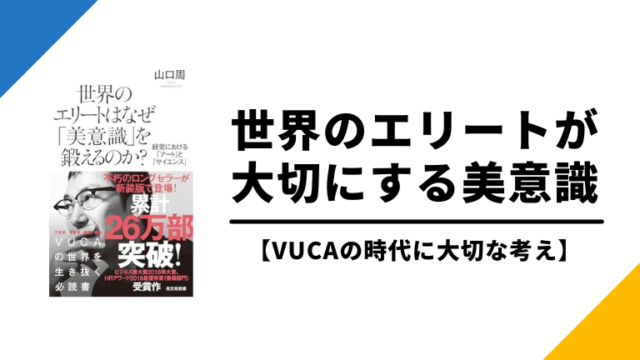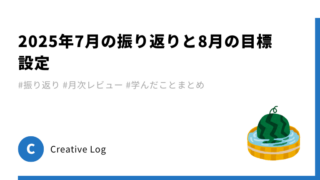苫野一徳さんの『親子で哲学対話~10分からはじめる「本質を考える」レッスン』を読んだので気になった部分を引用しつつ、学びをまとめます。
本質観取とは
本質観取とは、自分に訪れた確信を持ち寄ることで、みんなが納得できる「共通了解」を見出しあう営みのこと。
以下、本書より一部引用↓
本質観取とは、このように「わたしに訪れた確信」をもちよることで、みんなが納得できる”共通了解”を見出しあう営みです。<中略>「幸せ」にしても、「自由」にしても、「成長」にしても、「よい教育」にしても、同じです。わたしたちは、その本質を十分に言葉にできてはじめて、それを意識的に目指していくことができるようになるのです。
本質観取をすることにより、モノゴトの本質を言葉にできる。言葉にできるからこそ、その本質を意識的に目指すことができるようです。
哲学対話からの学びまとめ
- 本質観取のメリットについて理解できた
- 自分の思考パターンについて認識できた
- 本質にたどりつくまでのプロセスの大切さに気付いた
1. 本質観取のメリットについて理解できた
本書からの学び1つ目は、「本質観取のメリットを理解できた」ことです。以下、本書より一部引用します。
P. 45:「幸せ」にしても、「自由」にしても、「成長」にしても、「よい教育」にしても、同じです。わたしたちは、その本質を十分に言葉にできてはじめて、それを意識的に目指していくことができるようになるのです。
「本質を言葉にできれば、意識的に目指すことができる」というのは、確かにその通りだなと。理想とするイメージ(本質)を言語化しないとそもそも目指せないですもんね。
また、本質観取は対話を通じて「みんなが納得できる共通了解」を見出しあう営みです。なので誰かから押し付けられた価値観ではなく、みんなで作り出すプロセスが非中央集権的でとてもいいなと思いました。
2. 自分の思考パターンについて認識できた
本書からの学び2つ目は、「自分の思考パターンについて認識できた」ことです。
自分はこれまで「常識を疑う思考(批判的思考?)」はよくやっていました。たとえば「学校にいく必要ってあるの?」「1日8時間働く必要ってあるの?」などです。
そうではなく、フッサールの本質観取は「教育とは何か」「働くとは何か」という「常識の根っこ」にある本質を理解しようとしていました。人の考えを根本からひっくり返す感じがあってとても好きです。
■ 例
・学校っていく必要あるの? ← 批判的思考
・学校ってなに?そもそも教育とは? ← 本質観取
もちろん、批判的思考も本質観取も「どちらがいいか」という話ではないかと思います。それぞれ異なった役目があるので、タイミングによって使い分けていきます。
3. 本質にたどりつくまでのプロセスの大切さに気付いた
本書からの学び3つ目は、「本質にたどりつくまでのプロセスの大切さに気付いた」ことです。以下、本書より引用です↓
P.17 哲学の命は「なぁるほど、ここまでならたしかにだれもが深く納得できる!」という本質的な考えにたどり着くことにこそあるのです。
P.17 もちろん、絶対に正しい答えがあるわけではありません。でも、「なるほど、それはたしかにいえてる、本質的だ!」という深い洞察に、どこまでたどりつくことができるか。そこに、哲学の最も重要な命があるのです。
ここを読んで「本質よりも、本質にたどりつくまでのプロセスの方が大事なんじゃないかなぁ」ということに気付きました。
だから、生成AIとか使って「サクッと本質のようなモノにたどりつこうとする行為」は、ヘリコプターでいきなり富士山頂にいくようなものな気がして……登山という楽しみをまるっと無くしてしまっている行為な気がしました。
本質観取の「一番おいしいところ」は「本質にたどりつくまでのプロセス」→ これを知れたので、これからの学びや読書がより楽しくなりそうです。
#親子で哲学対話 #苫野一徳