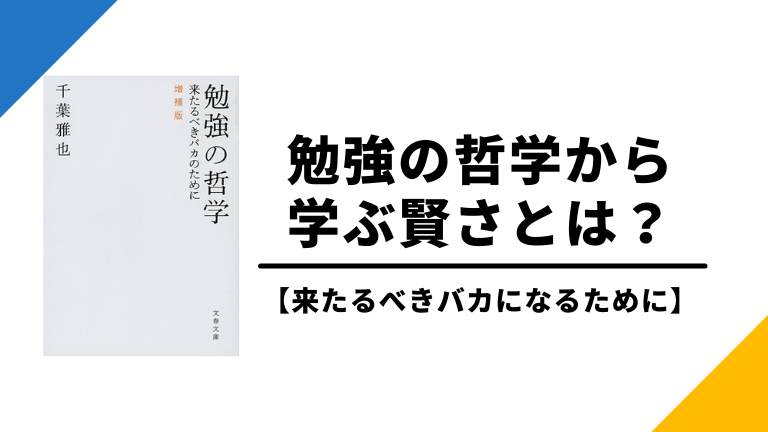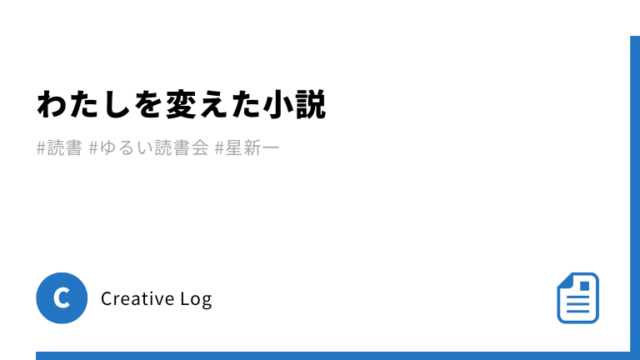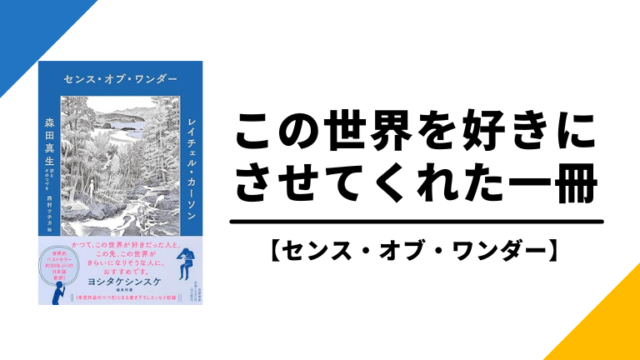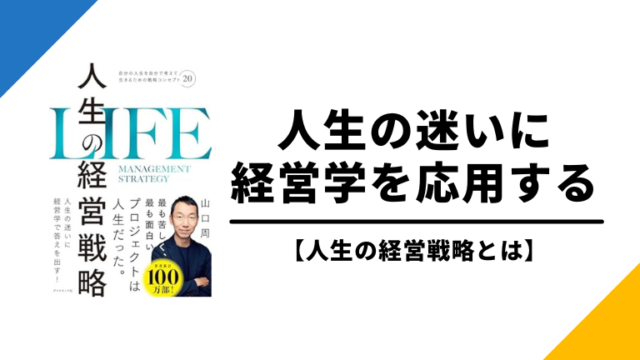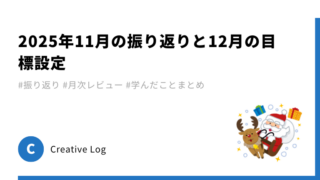千葉雅也著「勉強の哲学」を読んだので、勉強になった部分・印象に残った箇所をまとめます。
『勉強の哲学』を読んで学んだこと
- 勉強のスタンスが変わった気がする
- 不快な状態を楽しめるようになれそう
- 賢さとは何か?が深堀りできた
1. 勉強のスタンスが変わった気がする
P. 142 私たちは、比較を続ける人になろうとしている。だから私たちにとって、信頼に値する他者は、粘り強く比較を続けている人である。
この本を読んで
- 勉強は「仮固定」でもOK(というか、固定されることはない)
- だから「比較」をし続けるスタンスにしよう
と思うことができた。「勉強ってこれでもいいんだ!」と背中を押してもらった感じ。
また「もっと勉強そのものを楽しんでもいいのでは?」とも思えた(以下参照)。
P. 230 何をしているのか(意味)ではなく、動きそのものの面白さを鑑賞する芸術としてのダンスです。ダンスとして日々の出来事を見る。それは、出来事を目的性から解放し、出来事を自己目的的な運動として見る、ということです。
出来事や、勉強そのものの面白さ自体を味わえる人になりたい。子どもがクレヨンで線を書くこと自体を楽しんでいるように。
身軽にジャンルを飛び越えて比較し続けたい←
2. 不快な状態を楽しめるようになれそう
P.119 勉強というのは「問題意識をもつ」という、スッキリしない不快な状態をあえて楽しもう、それこそを享受しようとすることなのです。
ネガティブ・ケイパビリティきたー!という感じ(2025年はネガティブ・ケイパビリティに始まり、ネガティブ・ケイパビリティで終わる年なのかも)。
P. 228 エンタメ小説ならば、人のふるまいや出来事の意味を単純化することで成立しているところがあると思いますが、純文学では両義性や多義性が重視されていて、出来事をありのままの複雑さで、一方的に価値づけするような表現を避けてーー書こうとします。
- エンタメ小説→誰が見ても感じることは同じ
- 純文学→人によって感じ方が変わる(分かりにくい部分もある)
最近のコンテンツは「エンタメ小説」っぽいものが多い気がする。分かりやすくて・短時間で消化できるものの方がバズりやすいからそう見えているだけかも?
「よく分からない、難しい」ということから逃げずに、このような状態を楽しめるようになりたい。
3. 賢さとは何か?が深堀りできた
P. 118 勉強を進めるための基礎的なテクニックを説明します。アイロニーとユーモアを自分で自分に向ける、自分を構築している環境のコードに向けるという方法です。
自分を構築している環境のコードに目を向ける、という発想が目からウロコ。
でもこれはすごく難しい…だって自分を構築している環境なんて自分では分からないから。魚が「自分の周りには水がある」と認識するようなもの。
しかし、これをやると勉強を深めることができるようになるらしい。以下も合わせて参照。
P. 123 自分の状況は大きな構造的問題のなかにあり、自分一人の問題ではない、というメタな認識を持つことが勉強を深めるのに必須である。
P. 161 環境のノリによって即断せず、立ち止まって環境をメタに眺め、言語をアイロニー的・ユーモア的に使って、別の可能性をたくさん考える。これは、「賢く」なるということです。
ここで大切なのは「メタな認識」を持つということ。
自分だけが感じている課題も、自分だけの課題だと思わずに広い視点で見るようにしてみる。たとえば…
■ 今の自分の課題:
土日が雨だと子どもと一緒に過ごせる場所がない
■ 課題に感じている理由:
子どもたちの有り余るエネルギーを室内だけでは発散できない
■ メタな認識で考えてみる:
・雨だと子どもが遊べる場所がない
・町の子育て支援事業とかってあるのかな?
・町だけじゃなくて国の政策ってどうなってるの?
・ここを深堀りするには「社会学」とかが必要?
・他には「教育学」とかもありかも
↑これはアイロニー?
■ ユーモア的に考える
・そもそも雨でも外で遊べるのでは?
・雨だからこそできる遊びって何?
メタな認識を意識すると勉強が深まるとはこういうことかもしれない。
まとめ
今回は千葉雅也著「勉強の哲学」を読んで感じたことを3つに絞ってまとめました。
勉強に向かうためのスタンスを吸収したつもりですが、この本を読み終わって以下のポストにもある「完全に理解した」を思い出しました。
— 伊藤雄作 (@ito_yusaku) September 21, 2018
その分野を少し齧ると「完全に理解した」つもりになりやすい。けど、勉強を重ねると「何も分からない」という状態になる。
そこからさらに熟達すると、ようやく「チョットデキル」状態になる。勉強は「仮固定」でも構わないようですが、少しだけやって「完全に理解した」つもりにならないように気を付けたい。
#勉強の哲学 #千葉雅也