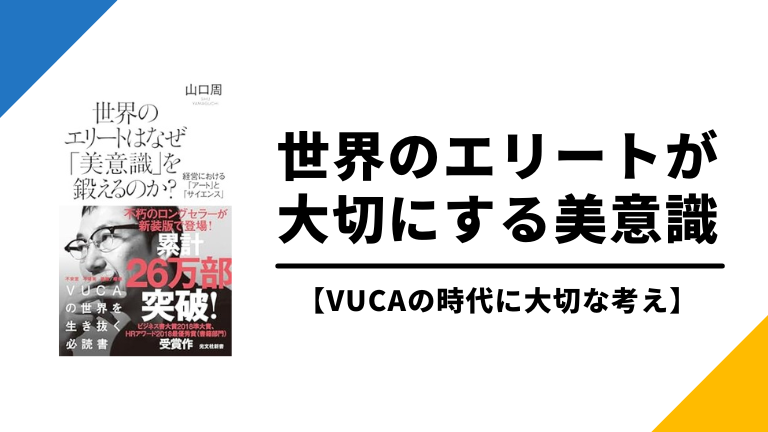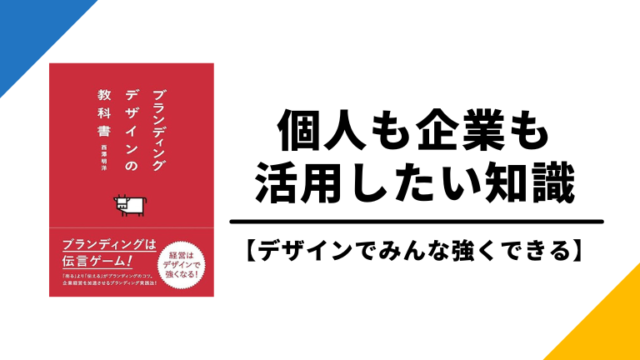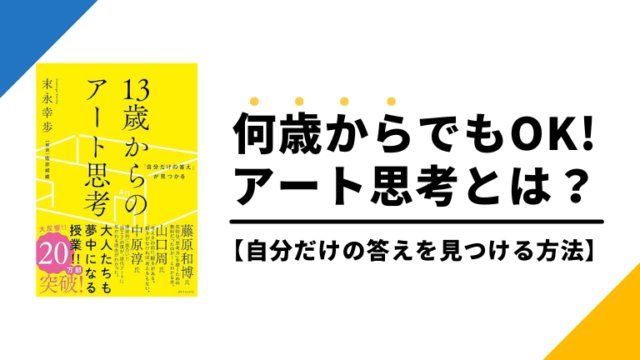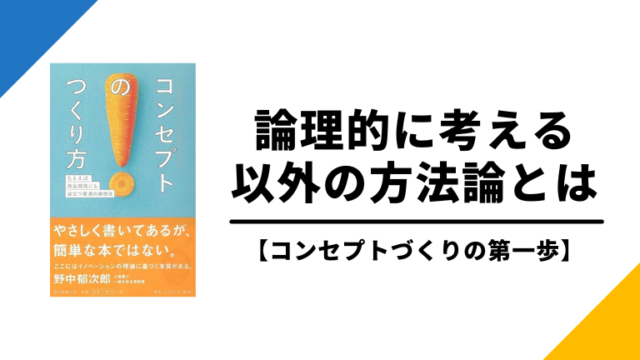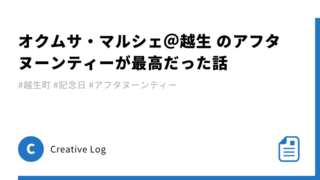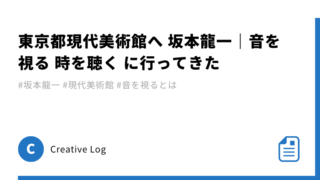山口周さんの「世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?」がおもしろすぎたので、学びポイントをまとめます。
「論理思考なんて当たり前でしょ?」「忙しくてアートなんてやってる暇ないよ…」と思っている人がいたらぜひ本書をおすすめします。
本書からの学びポイント
学びポイントが多すぎて書ききれないのですが、3つに絞ってまとめます。
- 論理と理性では勝てない時代になった
- 論理と理性に頼ると、正解がコモディティ化してしまう
- アートとサイエンスのバランスを取るのが大切
1. 「論理」と「理性」では勝てない時代になった
「もっと論理的に考えてみて」など社会人になってたくさん言われた気がしましたが、いつの間にか「論理や理性だけでは勝てない時代」に入ったようです。
以下、本書より引用。
私たち日本人の多くは、ビジネスにおける知的生産や意思決定において、「論理的」であり「理性的」であることを、「直感的」であり「感性的」であることよりも高く評価する傾向があります。
ビジネスにおいて「論理↔直感」「理性↔感性」という対象的なモードがあり、これらの中では「論理」「理性」が優位だと一般には考えられています。
自分自身も大学で化学専攻だったり、新卒で入社した会社でも研究職だったので「論理=最強」「論理的に考える=最優先」だと思っていたんですよね…
しかし、現在はそんなことはないと。
現代は不確実性の高い「VUCA」の時代。原因と結果が一対一で結びついている単純系ではなく、原因が多数存在する複雑系。様々な要素が複雑に絡み合う世界では論理思考のアプローチは機能しにくいのです。
だからこそ
- 全体を直感的に捉える感性
- 「美しい」と感じる打ち手を考える想像力
などが必要となってきます。
2. 論理と理性に頼ると、正解がコモディティ化してしまう
どういうことか。以下、一部引用します。
私たちは、物心ついた頃から、この「正解を出す技術」を鍛えられてきているわけですが、このような教育があまねく行き渡ったことによって発生しているのは、多くの人が正解に至る世界における「正解のコモディティ化」という問題です。
必死に「論理的かつ理性的」に意思決定する組織能力を高めた結果、皆が同じ戦場に集まって消耗戦を戦っているという、まるで囚人のジレンマのような状況に陥っているわけです。
論理的に正しい=理性的に正しい=正義、だと思っていたが、決してこの限りではない……ということに気付かせてもらいました。
たしかに「論理的かつ理性的」に判断し続けると、全員が同じ場所に到達しますよね。そうすることで「差別化」がどんどん難しくなる。
まず「論理と理性」に軸足をおいて経営をすれば、必ず他者と同じ結論に至ることになり、必然的にレッドオーシャンで戦うことにならざるを得ない。
これは企業だけでなく、個人にも当てはまる気がします。
現在は生成AIがどんどん進化しています。このままいくと、論理的に考えたアウトプットの質は間違いなくコモディティ化(同じクオリティになる)しますよね……
「ロジカルに考えて正解を選ぶようにしよう」より、心で考えて「合理性は一旦置いておき、自分のやりたいことってなんだろう?」と一度立ち止まって考えてみるべきかなと思います。
3. アートとサイエンスのバランスを取るのが大切
アートとは「直感・感性」のことで、サイエンスは「論理・理性」のことです。
「アート」は、組織の創造性を後押しし、社会の展望を直感し、ステークホルダーをワクワクさせるようなビジョンを生み出します。「サイエンス」は、体系的な分析や評価を通じて、「アート」が生み出した予想やビジョンに、現実的な裏付けを与えます。
「帰納」と「演繹」で考えてみれば、個別の現象から抽象概念へと昇華させる「帰納」は「アート」に、抽象概念を積み重ねて個別の状況へと適用する「演繹」は「サイエンス」が担うことになり、両者を繋ぎながら現実的な検証をするのが「クラフト」ということになります。
要は、どちらか一つだけではダメということ。アートのサイエンスの両方のバランスを取るのが大切。
サイエンスやクラフトだけでは、ワクワクするようなビジョンは生まれないし、数値で説明できないと「合理的じゃない」「前例がないよね」となって全て却下されてしまう。
とは言え、現代は「サイエンス」と「クラフト」が重視されていますよね(サイエンスは「論理的に考える・数値で考える」ことで、クラフトは「職人・経験」のようなイメージ)。
社歴が長い会社ほどこの傾向は強いのでは?
論理的に考えることは大切だし、経験も必要だけど、それだけだと新しいワクワクするようなビジョンは生み出せない。難しいところ。
サイエンスだけに立脚していたのでは、事業構造の転換や新しい経営ビジョンに打ち出しはできません。こういった不確実性の高い意思決定においては、どこかで「論理的な確度」という問題については割り切った上で、「そもそも何をしたいのか?」「この世界をどのように変えたいのか?」というミッションやパッションに基づいて意思決定することが必要になり、そのためには経営者の「直感」や「感性」、言い換えれば「美意識」に基づいた大きな意思決定が必要になります。
企業だけでなく、個人でも
- そもそも自分って何がしたかったのかな?
- 世界をどう変えていきたいのか?
など、直感や感性に従ってみるのも全然あり。というか、直感や感性に従った方がよりクリエイティブに考えられると思います。
自分の中に「美意識」という軸がないとどんどん理性に流されてしまう気がしたので、ときにはそもそも論に立ち返って自分の「美意識」を見直すことにします。
さいごに
これまで社会人になって「数値大事!KPIは絶対達成!」みたいなことを言われ続けて「なんか正しいんだけど、モヤモヤするな〜」と思っていたことをズバッ!と言語化してもらい気持ちのいい読後感でした。
2017年に出版された本だったとは…
2018年にビジネス書大賞とか受賞しているのも納得です。だって勉強になりすぎたし、おもしろすぎたから。出会えてよかった。
今月読んだ「現代アートがよくわからないので楽しみ方を教えてください」と合わせてアート熱が出てきたので、今年は美術館に足を運んでみようと思います。